ソウルライク――そのゲームジャンルは、プレイヤーに「死」と「再挑戦」を繰り返し求め、大きな達成感を提供する中毒性があります。しかし、一口に「死にゲー」と言っても、その難しさの質は作品ごとに大きく異なります。
「どの作品が一番難しいか」。
これは、常にゲーマー間で議論が巻き起こるテーマでしょう。
本ランキング記事では、単なるクリアのしづらさではなく、私自身がプレイを通して感じた「純粋なプレイヤースキルの要求度(システム難易度)」を最も重要な軸として、フロム・ソフトウェア作品を含む広範なソウルライクゲームの難易度を徹底比較しました。
つまり、レベル上げやマルチプレイなどの「救済措置」を乗り越え、プレイヤーの戦闘技術そのものが問われる作品ほど、ランキング上位に位置しています。
果たして、『SEKIRO』を筆頭とするフロムゲーの猛者たち、そして『Lies of P』などの新鋭ソウルライクの中で、最も高い壁として立ちはだかったのはどのタイトルなのか?
あなたの経験と照らし合わせながら、ぜひ最後までご覧ください。
⚔️ ソウルライク・フロムゲー 総合難易度ランキングTOP10
私自身の経験と、「システム難易度(プレイヤースキル要求度)」を最重要視した独自の判定基準に基づき、最も難しいソウルライクゲームのランキングを発表します。
| 順位 | タイトル | 難易度を決定づけた「壁」 |
| 1位 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 純粋なプレイヤースキル特化。忍殺必須の戦闘システムと、救済措置の皆無さ。 |
| 2位 | Lies of P | ディレイ攻撃によるシステムの学習コストの高さと、戦闘の「いやらしさ」。 |
| 3位 | Demon’s Souls | 「不便さ」が難易度に直結。回復アイテムの制限とセーブポイントの少なさ。 |
| 4位 | Bloodborne | ガードなしの攻撃特化スタイルへの転換を要求されるシステム。 |
| 5位 | DARK SOULS Ⅱ | 雑魚の数の暴力が序盤の難易度を押し上げている。ボスは比較的簡単。 |
| 6位 | DARK SOULS REMASTERED | マラソン難易度。中盤までのワープ制限とボスまでの道のりの長さ。 |
| 7位 | DARK SOULS Ⅲ | バランスの取れた難易度。スムーズな戦闘と適度な理不尽さが共存。 |
| 8位 | ELDEN RING | 「自由度」による難易度調整が可能。救済措置が多く、プレイヤーが難易度を下げられる。 |
| 9位 | 仁王 / 仁王2 | ハクスラ要素による難易度の逆転。戦闘スピードは速いが、装備でカバー可能。 |
| 10位 | アーマードコア6 | **アセンブルという明確な「正解」**があり、特定のボス戦以外は比較的難易度が低い。 |
💡 難易度ランキング考察:トップランカーの理由
ここからは、特に難易度の高い上位作品について、具体的な理由を深掘りします。
🥇 1位:SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
「サルが倒せず半年放置した」
従来のソウル系では、防御を固めたり、遠距離から攻撃したりと「ちまちま攻撃して時間をかければ勝つ」という戦法が通用しましたが、『SEKIRO』ではそれがほぼ不可能。「弾き」と「見切り」による体幹削り、そして「忍殺」が勝利の絶対条件です。
これにより、プレイヤーには「正しい行動」だけが強要され、逃げやビルドによる救済がありません。ボスの動きを完璧に覚え、システムを極めること、つまり純粋なプレイヤースキルのみが試される構造が、本作を文句なしの最難関にしています。
🥈 2位:Lies of P
「もう一度やりたいかと聞かれたら、やりたくない」
難易度の要因は、ボスが多用する「ディレイ攻撃(攻撃を意図的に遅らせる動作)」にあります。これは従来のソウルライクで培った反射的な回避やパリィのタイミングを、意図的にズラさせる、という非常に「いやらしい」設計です。
プレイヤーは、反射的な動作ではなく、「頭でタイミングを把握して意図的に遅らせる」という二重の負荷を強いられます。この引っかかりと、苛立ちを誘うシステムが、システム難易度を極端に高めています。
🥉 3位:Demon’s Souls
「回復がセーブポイントで回復しないのが面倒」
本作はフロムゲー初期作であり、その「システム的な不便さ」が難易度を押し上げています。
- 回復アイテム(草)が使い捨て: 消耗品であり、ストック管理が必要なため、マラソン(アイテム集め)の必要が生じます。
- セーブポイントの少なさ: ボスまでの道のり(マラソン)が非常に長く、途中でやられてしまうと精神的なダメージも大きくなります。
これは純粋な戦闘スキルというより、「システム的な煩雑さや縛り」によって難易度が上がっている、特異なケースです。
🔎 難易度ランキング考察:難易度を「選べる」下位グループ
ランキング下位の作品は、純粋なアクション要素だけで見れば難易度が高い側面もあります。しかし、豊富な「救済措置(RPG要素)」や「ゲームの自由度」により、プレイヤー自身が意図的に難易度を下げて攻略できる点が、総合難易度を相対的に下げています。
⑧ ELDEN RING:難易度調整の自由度が逸脱
「攻略順を間違えると難易度が跳ね上がるが、攻略順は選べる」
『ELDEN RING』は、広大なオープンワールドを導入したことで、これまでのソウルライクにはなかった「難易度を自分でコントロールできる」という要素を獲得しました。
- 強力な救済措置: 遺灰による囮(おとり)や、マルチプレイによる共闘が非常に強力です。また、攻略が難しいと感じたら、すぐに別のエリアへ移動し、レベル上げや強力な武器・遺灰の探索に時間を費やせます。
- ビルドの強さ: 序盤から手に入る明らかに強い武器や、強力な魔術・祈祷といった「壊れ」ビルドが存在するため、プレイヤースキルが未熟でも、火力とシステムでゴリ押しが可能になります。
本作の戦闘システム自体の難易度は高いですが、プレイヤーに与えられた「選択肢の多さ」が、総合的なハードルを大きく下げています。
⑨ 仁王 / 仁王2:ハクスラによる難易度の逆転
「装備が整ってくればだんだん楽になってくる」
『仁王/仁王2』の戦闘は、フロムゲーとは一線を画す「超高速」かつ「複雑なシステム(残心など)」を持っており、システム難易度自体は非常に高いと言えます。しかし、ランキングが下位に位置するのは、「ハクスラ(ハックアンドスラッシュ)」というRPG要素の存在です。
- 装備ゲーとしての側面: 敵を倒して強力な武器や防具を厳選し、装備が整うとプレイヤーのステータスが劇的に向上します。システムを極めるよりも、装備を整えることで難易度を緩和できる余地が大きく、これがソウルライク初心者にとっての救済措置となります。
- マルチの充実: プレイヤー同士の共闘も容易であり、高速戦闘のプレッシャーを仲間と分散できる点も、難易度を下げる大きな要因です。
その他の中堅・下位グループについての考察
- DARK SOULS II (5位):
雑魚の配置は悪意に満ちていますが、ボス自体は攻撃パターンが単調で、ゴリ押し可能なダメージ量も多いため、ボス戦のシステム難易度は低めでした。 - DARK SOULS Ⅲ (7位):
システムのスムーズさ、ボスのバリエーション、セーブポイントの配置などが「ちょうどいい」バランスであり、シリーズ経験者にとっては最も快適に遊べる難易度となっています。 - アーマードコア6 (10位):
「アセンブル(機体構成)」という明確な解法があり、アクションスキルよりもビルド構築力が重視されます。このアセンブルという救済措置があるため、総合的な難易度は最下位となりました。
✅ 結論:真の難しさは「システム習熟」と「達成感」にあり
本ランキングを通して、ソウルライク・フロムゲーの難易度は、単なるボスの強さだけでなく、「システム難易度(プレイヤースキル要求度)」、「救済措置の有無」、そして「システム的な不便さ」の組み合わせによって決定されることが明確になりました。
ソウルライクの頂点は「回避」ではなく「直面」
総合ランキングの頂点に立った『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』は、レベル上げやマルチプレイといったRPG的な救済措置を排し、プレイヤーに「弾き」と「忍殺」というシステムの習熟だけを強く求めました。この戦闘からの逃げ道をなくす設計こそが、純粋なプレイヤースキルの壁として、多くのゲーマーにとって最も高い難易度となった理由です。
また、『Lies of P』もディレイ攻撃という形で、従来のソウルライクの経験則を否定し、新たなシステム習熟を求めることで、高い難易度を築き上げました。
一方で、『ELDEN RING』や『仁王』のように、システム難易度が高くても、自由度やハクスラといった「救済措置」が充実している作品は、プレイヤーが意図的に難易度を緩和できるため、総合ランキングでは下位に位置づけられました。
難易度は「乗り越えた喜び」に変わる
私自身が『SEKIRO』でサルに敗れ半年放置した経験のように、ソウルライクの難しさは時にコントローラーを投げたくなるほどの理不尽さを感じさせます。しかし、その高いシステム難易度を乗り越え、「できなかったことができるようになった」と実感できた瞬間の喜びこそが、ソウルライクゲームが持つ唯一無二の魅力です。
あなたがソウルライクの壁に直面した時、どの作品で最も大きな達成感を得たでしょうか?

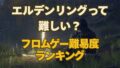
コメント